「勇気づけ」とは何か?アドラー心理学の核心を学ぶ(塾長 永倉)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。
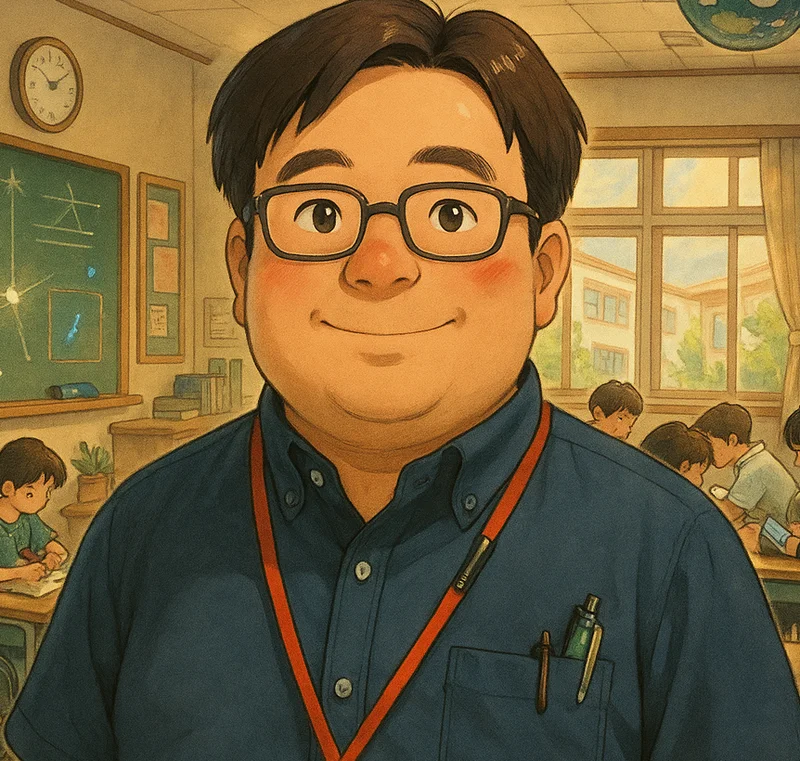
永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
体験授業はコチラ↓
今回よりシリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書こうと思います。
どうぞ、宜しく御願い致します。
第1回は、
「勇気づけ」とは何か?アドラー心理学の核心を学ぶ
です。

■ 「教育とは何か?」という問いに立ち返る
「もっと勉強しなさい」
「ちゃんとしなさい」
「ほら、◯◯ちゃんはできてるよ」
こうした言葉が、教育の現場や家庭ではよく使われます。
しかし、アドラー心理学の観点から見ると、
これらはすべて「やる気を削ぐ言葉」と言えるのです。
アドラー心理学において、
教育の目的は単なる成績向上ではありません。
それは、
子どもが社会の中で貢献感と自己効力感を持ち、
自ら課題に向き合う力を育むことです。
この考え方の中核にあるのが、
勇気づけ(Encouragement)という概念です。
■ 「勇気づけ」とは何か?
勇気づけとは、
困難を克服するための力を引き出す働きかけです。
ここで言う勇気とは、
戦う勇気でも、
競争に勝つための気合いでもありません。
それは、
「たとえうまくいかなくてもやってみよう」
と思える前向きな心のことです。
アドラーが言う
勇気づけとは、
子どもが失敗を恐れずに
挑戦し続ける姿勢を支える
コミュニケーションなのです。
■ 褒める vs 勇気づけの違い
多くの人は「褒める」ことが
良いことだと思っています。
しかしアドラー心理学では、
褒めること=上から目線の評価だと捉えます。
「すごいね、100点取れて」
「えらいね、早く宿題終わらせたんだ」
これらは一見前向きな声かけに見えますが、
「評価しているのは親や先生」という構造が
無意識に刷り込まれていきます。
一方で、
「勇気づけ」は評価ではなく、
観察と共感による事実のフィードバックです。
「毎日コツコツやってた成果が出たね」
「わからなかったところに挑戦してたの、見てたよ」
「やるって決めて、自分で机に向かってたね」
このような言葉は、
「あなたの努力や成長に価値がある」
と伝える力になります。
■ 他業界の事例:なぜGoogleは「勇気づけ文化」で伸びたのか?
Googleは、
社内で「心理的安全性」を重視する文化を構築しています。
その要となっているのが、
勇気を持って発言できる場の提供です。
社員が自由に提案し、
間違いを恐れず発言できる文化があるからこそ、
革新的なアイデアが生まれるのです。
これはまさに、
アドラーの「勇気づけ」が組織で応用されている好例です。
教育現場でも、
子どもが「間違っても大丈夫」「挑戦していい」と思える環境が整えば、
潜在的な力が引き出されるのは間違いありません。
■ 教育現場で実践できる「勇気づけ」の3ステップ
① 行動に注目する
→ 成果よりもプロセスや意志に注目し、声をかける。
② 比較しない
→ 他人との比較で優劣をつけるのではなく、
昨日の自分との変化を伝える。
③ 見守る勇気を持つ
→ 勇気づけは干渉」ではなく信頼です。
見守りながら支える姿勢が求められます。
■ 最後に:あなたが、勇気づけされていた瞬間は?
あなた自身が誰かに
「大丈夫、きっとできるよ」と
背中を押してもらった経験はありませんか?
その経験こそ、教育の本質です。
アドラー心理学は、
子どもだけでなく、
指導する側の私たちにも
勇気をくれる学問です。
まずは、今日このあと、
子どもにひとつ、
勇気を引き出す言葉をかけてみてください。
きっと、子どもの目が変わるはずです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

明倫館塾長
永倉秀樹


