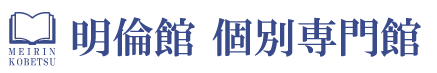つながりが子どもの心を支える(塾長)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。

永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
過去のコラム↓
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第4回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
アドラー×教育シリーズ↓
アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp

■ なぜ今「孤立しない子育て」が重要なのか?
スマートフォンが普及し、SNSが日常になった今、子どもたちは以前よりも、つながっているように見えます。しかし、実際には、「人とのつながりを感じられない」子どもが増えているという報告が多数あります。アドラー心理学では、こうした孤立感を乗り越える鍵として、「共同体感覚(sense of community)」という概念を重視します。
■ 「共同体感覚」とは何か?
アドラーが提唱した「共同体感覚」とは、「自分は社会の一員であり、役に立てる存在だ」という感覚のことです。この感覚を持つことで、子どもは、「自己肯定感が高まる」「他人を信頼できるようになる」「協力的・社会的な行動がとれるようになる」などの大きな成長を遂げるとされています。
■ 他業界の事例:企業の心理的安全性とチームビルディング
GoogleやAmazonなどの大企業では、「心理的安全性」の高い職場環境づくりに力を入れています。これは、「この場所では自分の意見を言っても大丈夫」「自分は受け入れられている」という信頼の文化を築くことです。この考え方はそのまま、教育にも当てはまります。子どもにとって「家庭」や「学校」が安心できる場であり、「自分はここにいていい」と思える場所であること。これがまさに、教育における共同体感覚の基盤なのです。
■ 「所属感」と「貢献感」の両輪を育てる
アドラー心理学では、共同体感覚は以下の2つの柱から成り立つとされています。
◎ 所属感:「自分はここにいていい」と思える安心感
→ 家庭での何気ない会話や、学校での役割分担が育てる
◎ 貢献感:「自分は誰かの役に立っている」と思える自信
→ 掃除当番、下級生へのサポートなど、小さな経験の積み重ねが重要
■ 実践:家庭でできるつながりを育てる工夫
| 実践内容 | 解説 |
|---|---|
| 子どもに家の仕事を頼む | 例:食器を並べる、洗濯物をたたむなど。「助かったよ」「ありがとう」が貢献感を育てます。 |
| 家族会議を開く | 子どもも家庭の一員として意見を聞く。「どう思う?」という一言が対等な関係を作ります。 |
| 学校以外の“所属先”を作る | 習い事や地域活動も「自分の居場所」になります。学校だけに依存しない環境づくりを。 |
■保護者にできる共同体感覚の育て方
失敗しても受け入れられる「安心の場」をつくる
子どもの話を「正しい/間違い」ではなく「気持ち」として聴く
「役に立ってるね」「ありがとう」を習慣にする
こうした小さな積み重ねが、子どもの心の土台を安定させ、他者と信頼関係を築く力へと育ちます。
■ 孤立しない子は、学び続ける力がある
人は、つながりの中でこそ、安心して挑戦でき、失敗を乗り越えることができます。
アドラーの言う「勇気づけ」は、単なる励ましではなく、「あなたはこの社会の一員だよ」という深いメッセージなのです。
■ 「つながり」が学びのエネルギーになる
・共同体感覚は「自己肯定感」の源泉
・家庭と学校は“安心できる所属先”になるべき場所
・貢献経験が「自分には価値がある」という感覚を育てる
アドラーの言葉に、こんなものがあります。
「人間のすべての悩みは、対人関係の悩みである」
その逆もまた真実です。
すべての成長も、信頼ある関係の中から生まれるのです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

明倫館塾長
永倉秀樹