叱らない指導の誤解と本質(塾長 永倉)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。
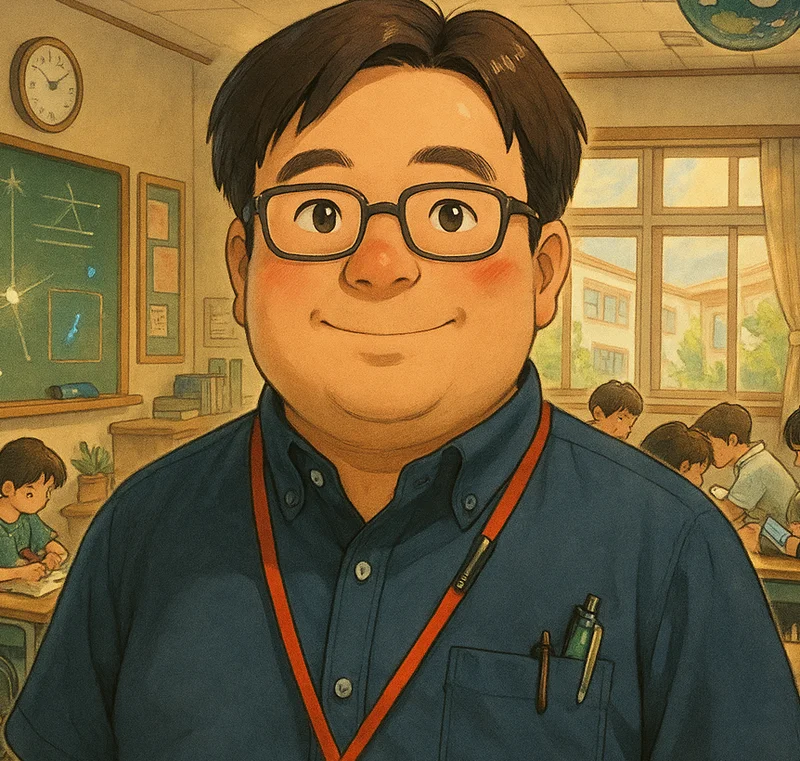
永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
体験授業はコチラ↓
過去のコラム↓
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第3回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
アドラー×教育シリーズ↓
アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp
■ 「叱らない教育」は甘やかしではない
近年、「叱らない子育て」「褒めて伸ばす教育」が注目されています。
しかし、アドラー心理学を深く理解していないまま表面だけをなぞると、
何でも許す=優しいという誤解を生みかねません。
アドラー心理学の目指すところは、
「支配しない教育」であり、「責任と自由をともに与える教育」です。
つまり、「叱らない」とは「無責任に放任すること」ではなく、
「子どもと対話しながら責任を育てること」なのです。

■ アドラーが大切にした「対等な関係性」
アドラーは、教育の理想は「対等な人間関係」にあるとしました。
これは、子どもに迎合するという意味ではなく、
子どもを1人の人格として尊重する姿勢を指します。
たとえば、こんな違いがあります。
| 管理型の指導 | 対話型の関わり |
|---|---|
| 「早くやりなさい!」 | 「何から始める予定?」 |
| 「何で忘れたの!」 | 「何が原因だったと思う?」 |
| 「もう知らない!」 | 「次はどうしたら防げると思う?」 |
命令や叱責は一時的に行動を変えるかもしれませんが、
内面の変化を促すのは対話だけです。
■ 他業界の事例:マネジメントにおける「コーチング型リーダー」
近年、企業経営の現場でも、
叱らないマネジメントがスタンダードになりつつあります。
特に注目されているのが「コーチング型リーダーシップ」です。
これは部下に命令せず、
問いかけと傾聴を通じて、
自発的な行動と責任感を引き出す手法です。
例えば、グーグルやユニリーバでは、
「部下の成長を促す対話力」が管理職の評価基準にもなっています。
これとまったく同じ考え方が、
アドラー心理学における叱らない教育にも当てはまるのです。
■ 子どもは叱られた内容よりも態度を記憶している
実際、子どもたちは「どんなことで叱られたか」よりも、
「どんな態度で」「どんな口調で」言われたかを強く記憶しています。
強い口調で叱られると、
内容よりも「自分は否定された」という感情が心に残ってしまい、
学びや行動改善よりも、
「親や先生を避けよう」という方向に向かってしまうのです。
■ 実践:叱る代わりに使いたい“問いかけの言葉”
以下のような「考えさせる問い」は、子どもに気づきを与えます。
「今、どんな気持ちだった?」
「どうすれば、もっと良くできそう?」
「次に同じことが起きたら、どうしたい?」
これらは単なる注意ではなく、
思考力と自己責任を育てる教育的な言葉です。
■ それでも、叱らないといけない場面がある時は?
もちろん、安全や命に関わるような場面では、
はっきりと「ダメ」と伝える必要があります。
ただし、そのときも
「あなたが大切だからこそ、危険なことはしてほしくない」
「叱るのは怒っているからじゃなくて、守りたいからなんだ」
という関係性を守る言葉を添えることが大切です。
■ 子どもは「叱られること」で成長するのではない
アドラーはこう言います。
「子どもは、信頼され、尊敬されることで責任を学ぶ」
つまり、信頼こそが最高の教育資源なのです。
■ まとめ:叱る前に、対話をする勇気を
「叱る」ではなく「考えさせる」問いを
「命令」ではなく「対話」で関係を築く
「支配」ではなく「信頼」で導く
これがアドラーが教える、叱らない教育の真の意味です。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

明倫館塾長
永倉秀樹

