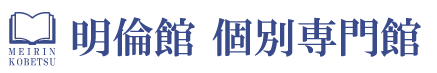子どもが立ち直る「勇気の言葉」とは(塾長)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。

永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
過去のコラム↓
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第5回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
アドラー×教育シリーズ↓
アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp

■ 「失敗=ダメなこと」ではない世界を
私たちは多くの場合、「失敗しないこと」を良しとする文化の中で育ってきました。テストの点、模試の偏差値、受験の合否…。しかし、子どもが本当に学びを得るのは、*「失敗したとき」です。アドラー心理学はこのように説きます。「失敗は学ぶために不可欠な体験である。失敗そのものが問題なのではなく、失敗をどう捉えるかが重要である」つまり、失敗は挫折ではなく成長のきっかけなのです。
■ 「失敗=評価が下がる」と感じさせないために
子どもが失敗を恐れる理由の多くは、「怒られるのでは」「がっかりされるのでは」「自分はダメな人間だと思われるのでは」といった他者からの評価に起因しています。この評価不安を和らげるには、大人の声かけや関わり方がポイントになります。
■ 他業界の事例:スタートアップ企業に学ぶ「失敗歓迎文化」
スタートアップ業界では、「失敗」はむしろ歓迎されます。なぜなら、失敗から得られる検証データが、次の改善につながるからです。例えばAmazonやAirbnbでは、「小さな失敗を迅速に経験し、その結果を学習として取り込み、柔軟に修正して再挑戦する。」このPDCA型マインドが成功のポイントとなっています。教育も同じです。子どもが「ミスをしても学べる」「また挑戦できる」と思える環境をつくることが、真の成長につながります。
■ 実践:失敗に対する声かけを変えるだけで、子どもは変わる
以下のような声かけは、子どもの「立ち直る力(レジリエンス)」を育てます。
| 一般的な反応 | アドラー的な声かけ |
|---|---|
| 「なんでこんなミスしたの?」 | 「どこでつまずいたと思う?」 |
| 「また間違えたの?」 | 「この経験から何がわかりそう?」 |
| 「ちゃんとやってよ!」 | 「次はどうすればいいと思う? |
ポイントは、評価せず、学びの視点を共有すること。子どもが「この失敗は意味がある」と思えれば、次へのエネルギーに変わります。
■ 子どもが失敗した直後に避けたい言葉
「そんなこともできないの?」「前にも言ったよね?」「あきれるよ…」これらは、子どもの勇気をくじく言葉です。その場で反省させるよりも、「次にどうするか」に意識を向けさせることが大切です。
■ 失敗を認めることで、信頼関係が深まる
大人も、自分の失敗や過去の苦い経験を、子どもにあえて語ってみましょう。「パパも昔、テストで30点取ったことあるよ」「ママも仕事で失敗して怒られたことあるよ」
こうした話は、子どもにとって「完璧じゃなくていい」と思える安心感を与えます。それが、信頼の土壌となり、子どもの挑戦心を支えてくれます。
■ 教育に必要なのは「ミスの数を減らすこと」ではなく…
ミスを通して、「原因を分析する力」「修正する力」「持ち直す力(メンタル)」を身につけること。この学びの循環を育てるのが、アドラー的教育の真髄です。
■ まとめ:失敗は「勇気づけ」のチャンス
・ミスを責めるのではなく、気づきを促す
・失敗に対する「意味づけ」を大人が変える
・立ち直る力(レジリエンス)を育てる言葉を使う
アドラーの言葉にこうあります:「勇気づけとは、困難を克服する力を与えることである」失敗は、まさに困難の中にあります。だからこそ、その瞬間こそが、最も勇気づけが必要なタイミングなのです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

明倫館塾長
永倉秀樹