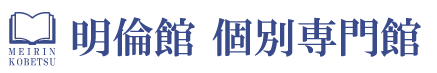子どもを信じる力が、未来を変える(塾長)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。
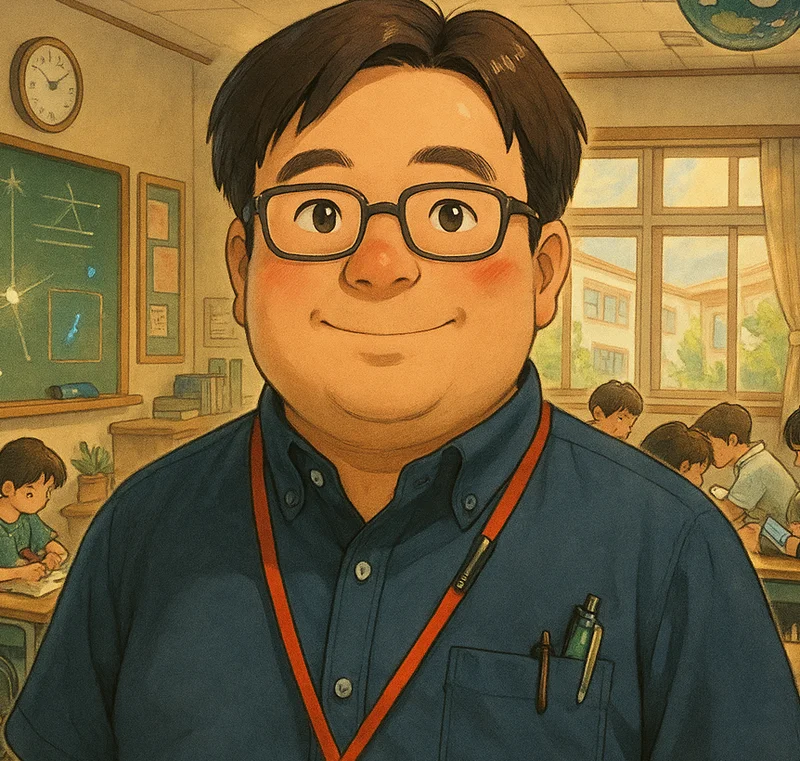
永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
過去のコラム↓
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第7回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
アドラー×教育シリーズ↓
アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp

■ 子どもは、見られ方で変わる
アドラー心理学では、教育においてもっとも重要なのは「勇気づけ」であるとされています。勇気とは、「困難を克服する力」「一歩を踏み出す心」です。それを与えるのが、親や教師の関わり方なのです。アドラーはこう言います、「子どもは、信じられることによって、自分を信じるようになる」つまり、大人が子どもをどう“見ているか”が、その子の自己像を決めるということです。
■ 「褒める」と「勇気づけ」はどう違う?
一見似ているこの2つの言葉、アドラー心理学でははっきりと区別されます。
| 褒める(Praise) | 勇気づけ(Encouragement) |
|---|---|
| 上からの評価 | 対等な関わり |
| 条件付き(成果重視) | 条件なし(努力・姿勢重視) |
| 「すごいね!」 | 「がんばったね」 |
| 承認を求める依存を生む | 自立・内発的動機を育てる |
褒めることは悪ではありませんが、「他者の評価」に依存しやすくなります。勇気づけは、子どもの内面にある、やる気の火種に息を吹き込む行為です。
■ 他業界の事例:一流スポーツコーチが行う勇気づけ指導
日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、選手のパフォーマンス以上に「選手本人の可能性」に目を向け、信頼を言葉で伝え続けるスタイルで知られています。「お前なら絶対できる」「楽しんでこい」「失敗してもいい。次がある」こうした声かけは、選手の自己効力感を高め、結果的に能力の発揮へとつながります。教育現場にも通じるエッセンスがここにあります。
■ 教室や家庭でできる勇気づけの言葉
「やってみようとしてたの、見てたよ」
「そこまで工夫したんだね」
「ミスしても、前より落ち着いてたね」
「自分で考えて動いてるのがわかるよ」
これらは結果ではなく、努力のプロセスや姿勢を見て伝える言葉です。評価ではなく、信頼と共感が軸になっています。
■ 勇気づけの本質は「存在承認」
子どもにとって何よりも大切なのは、「自分はここにいていい」「自分は価値のある存在だ」と感じられること。
成績がよい・悪い
言うことを聞く・聞かない
そういった条件ではなく、存在そのものが認められているという感覚。これこそが、アドラーが言う勇気づけの核心です。
■ 勇気づけが生む“自己効力感”
「自己効力感(Self-efficacy)」とは、「自分にはできる」という感覚のこと。これは、アメリカの心理学者バンデューラが提唱した概念で、アドラーの考えと深く通じ合っています。自己効力感の高い子は、「挫折しても立ち直る」「新しい挑戦を恐れない」「自分で考え、自分で決めることができる」など、生きる力そのものに強くなります。
■ 子どもを信じるとは「できる」と伝えること
・結果ではなく「プロセス」や「姿勢」に目を向ける
・条件付きの褒め言葉より、無条件の信頼の言葉を
・「存在承認」と「自己効力感」を育てることが、子どもの未来を支える
アドラーは最後にこう述べています「人は、勇気を与えられたとき、変わりはじめる」
変わるのは、子どもだけではありません。勇気づけを実践する大人自身も、教育の喜びを再発見することになるのです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

明倫館塾長
永倉秀樹