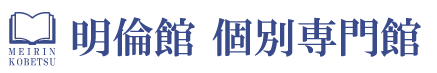フィンランドに学ぶ新しい学びのかたち(塾長)
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。

永倉の自己紹介はコチラ↓
明倫館の夏期講習はコチラ↓
過去のコラム↓
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第8回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
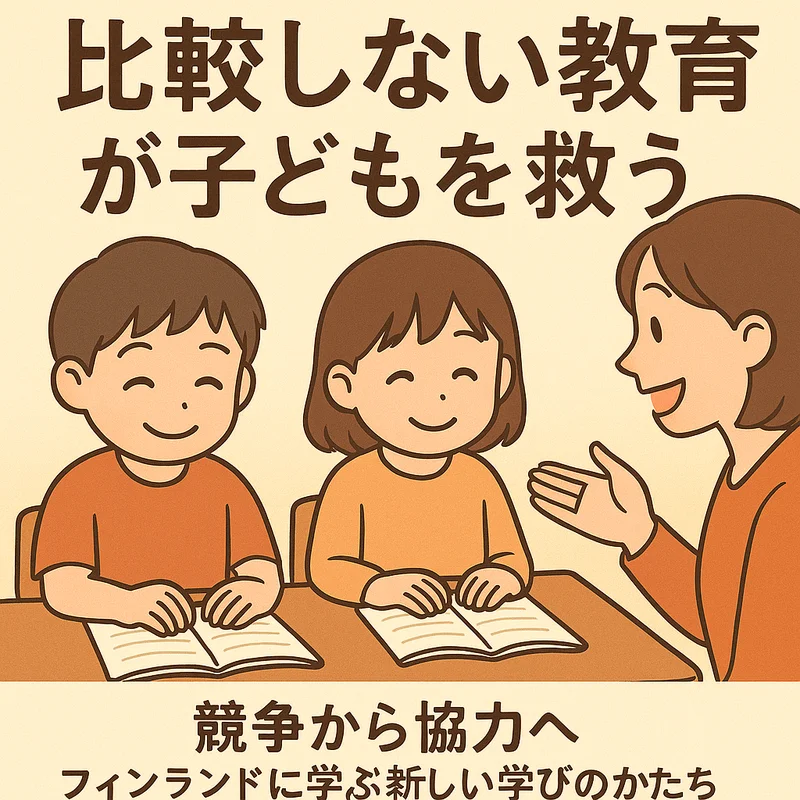
アドラー×教育シリーズ↓
アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp
■ なぜ「比べる教育」は子どもの力を奪うのか
「〇〇ちゃんより遅いね」
「あの子はもっとできてるよ」
「なんで兄弟はできるのに…」
こうした比較の言葉は、子どもにとって自尊心を大きく傷つける原因となります。
アドラーはこう述べています。
「人の悩みはすべて対人関係の悩みである」
そして、その悩みの多くは、他人と自分を比べることから生まれるのです。
■ 比較の教育がもたらす3つの問題
① 劣等感が根づく
→「自分はダメだ」「どうせムリ」という思考パターンが形成される。
② 他者の成功を喜べなくなる
→「嫉妬」や「無力感」が生まれ、協力や共感の力が育たない。
③ 内発的動機が失われる
→「勝つため」「褒められるため」に行動するようになり、やがてやる気が消える。
■ 他業界のヒント:フィンランド教育の「非競争主義」
PISA(学習到達度調査)で世界トップクラスの成果を出すフィンランド。その教育の核にあるのが、「他人と比べない」「点数化しない」「競争させない」という考え方です。特徴的な取り組みは、「成績表に順位をつけない」「テスト結果は本人と先生だけが共有」「他人と比べず、自分の中での成長に注目」です。このような教育の中で育った子どもたちは、自己肯定感が高く、学ぶことを楽しむ力が強いと言われています。
■ アドラー心理学とフィンランド教育の共通点
アドラー心理学の核:「共同体感覚」
→ 自分が社会の中で役に立っているという感覚
フィンランド教育の核:「全員が学びの共同体の一員」
→ 他人と競うのではなく、助け合いの中で成長していく
つまり、「比較ではなく協力」が、子どもの安心感とやる気を育てるのです。
■ 家庭でできる比較しない声かけ
| よくある声かけ | アドラー的な変換 |
|---|---|
| 「〇〇くんはもっとできてるよ」 | 「前より早くできるようになったね」 |
| 「クラスで何番だった?」 | 「自分でどう思った?」 |
| 「弟はちゃんとできてるよ」 | 「昨日よりうまくいったところ、あった?」 |
「他人との比較」から「昨日の自分との比較」へ。この視点の転換が、子どもを大きく変えていきます。
■ 「競争」ではなく「成長」を喜ぶ文化へ
・点数よりも「理解したプロセス」
・勝ち負けよりも「挑戦した勇気」
・結果よりも「努力を続けた姿勢」
このような価値観を、家庭や塾で育んでいくことで、子どもは、安心して学べる土壌を手に入れます。
■ 「他人と比べない」ことは、最大の勇気づけ
アドラーはこう言っています。
「劣等感は、他人と比べることによって生まれる」
だからこそ、比べない教育こそが子どもの本来の力を最大限に引き出す鍵なのです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!
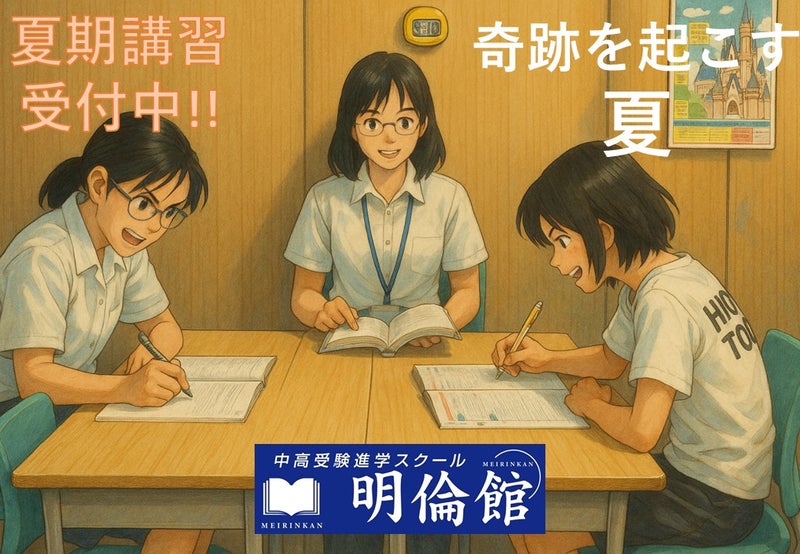
明倫館塾長
永倉秀樹