アドラーが教える「見守る勇気」とは
こんにちは
明倫館塾長の永倉です。
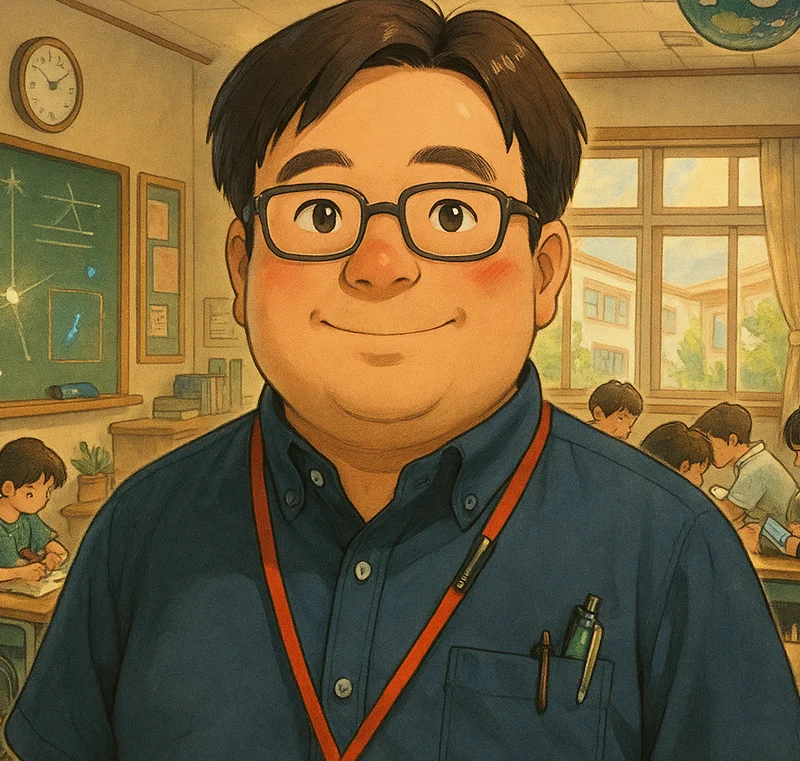
永倉の自己紹介はコチラ↓『明倫館塾長永倉の自己紹介です。』明倫館塾長のブログをご覧頂き誠にありがとうございます。 明倫館塾長の永倉と申します。 明倫館小鹿教室のブログ明倫館本部教室のブログも書いておりますが 塾長とし…ameblo.jp
シリーズで
子どもの力を引き出す!アドラー心理学×教育 実践ガイド
について書いております。
本日は、第9回となります。
どうぞ、宜しく御願い致します。
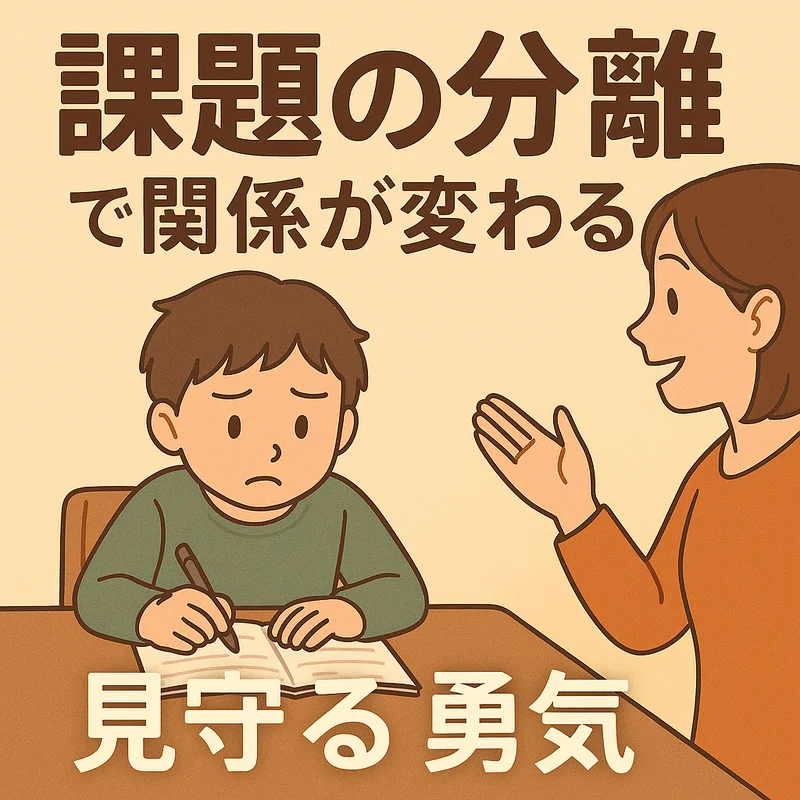
アドラー×教育シリーズ↓アドラー心理学×教育|塾名が明倫館だから館長じゃね?と思っている塾長の日記ブログ明倫館塾長の永倉さんのブログテーマ、「アドラー心理学×教育」の記事一覧ページです。ameblo.jp
■ 子育てや指導でありがちな「やりすぎ」のワナ
「宿題やったの?」「テスト勉強したの?」「忘れ物しないようにチェックした?」「そんなんじゃ将来困るよ!」 つい、子どものやるべきことにまで踏み込んでしまう。親なら誰しも経験があると思います。でも、それは、「大人が背負う必要のない課題」にまで口を出している状態かもしれません。アドラー心理学では、これを「課題の分離」と呼び、明確な線引きを重視します。
■ 「課題の分離」とは何か?
アドラーはこう定義します。「その選択の結果を最終的に引き受けるのは誰か?」この問いを基準に考えたとき、たとえば「勉強しない」という選択の結果(点数が下がる、理解が遅れる)を最終的に引き受けるのは子どもです。つまり、勉強するかしないかは「子どもの課題」であり、大人が無理やり手を出すべきものではないのです。
■ 他業界の事例:トヨタの「現場主義」
トヨタ生産方式では「現場・現物・現実」の三現主義が有名です。マネージャーは手を出す前に、「その現場を見て、自分の課題かどうかを判断する」という徹底した姿勢を持っています。この思想は、教育にも応用できます。「子どもの失敗=親や教師が背負う課題ではない」という視点を持つことで、子ども自身の責任感と主体性が育ちます。
■ 親や教師がやるべきは「境界線を引く」こと
| 課題の種類 | 誰の課題か | 大人の対応 |
|---|---|---|
| 勉強する・しない | 子ども | 結果を見守る |
| 挨拶をする・しない | 子ども | モデルとなるだけ |
| 友達とどう関わるか | 子ども | 助言はできるが、介入しない |
| 安全な環境を整える | 大人 | 当然の責任 |
| 愛情を注ぐ・見守る | 大人 | 自分の選択として行う |
ポイントは、「干渉しない=放任」ではなく、「尊重する」こと。
■ 見守る勇気を持つための3つのコツ
① 「助けたくなる衝動」に気づく
→「今、私はこの子の課題に手を出そうとしている?」と一歩立ち止まる
② 「困る経験」をさせる
→失敗しても、「そこから学ばせること」が最も価値ある成長
③ 「やらせる」ではなく「選ばせる」
→「どうするかはあなたが決めていい。でも、結果は自分で引き受けてね」と伝える
■ 子どもとの関係がラクになる
課題を分離できるようになると、
・過干渉による親子バトルが減る
・子どもが「自分で責任を持つ」ようになる
・教師は「支援者」としての立場を明確に持てる
つまり、お互いが自立した関係性を築けるのです。
■ まとめ:「支配」ではなく「尊重」が関係を変える
アドラー心理学の「課題の分離」は、親や教師が「責任を手放す」ことで、信頼関係が深まるという逆説的な知恵です。「子どもは、任されたときに責任を持つようになる」 大人の見守る勇気が、子どもの引き受ける勇気を育てるのです。
最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!
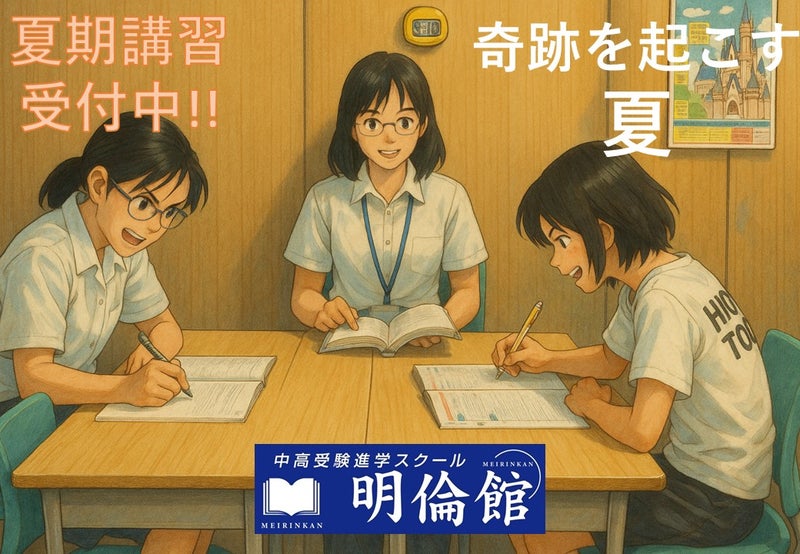
明倫館塾長
永倉秀樹


